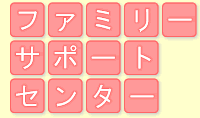イベント報告
イベント報告
2025/12/01
提供会員勉強会 【第1部】作ってみよう!バルーンアート 【第2部】茶話会 養育協力家庭発表会
 日時:2025年11月28日(金)
日時:2025年11月28日(金)
場所:こども家庭センター「たまっこ」2階活動室
第1部講師:スマイルバルーンの皆様
第1部では、ボランティアセンターや市内の施設・コミュニティセンターの依頼を受け、各種イベントでバルーンアートの活動をされているスマイルバルーンの皆様を講師としてお招きしました。細長いカラフルな風船を、キュッキュッとねじっていき、子どもたちに大人気の剣、犬、うさぎ、お花を作って楽しみました。
始めは細長い風船に空気を入れるだけでドキドキでしたが、スマイルバルーンの皆様の熱心なご指導の下、より見栄え良く、かわいい作品にしたいと夢中になって取り組みました。
作品を作りながら、参加された会員さん同士も自然に打ち解け、和やかな雰囲気の中あっという間の1時間半となりました。
第2部では、多摩市の「子どもショートステイ事業」で、お子さんをご自宅にてお預かりしていただいている養育協力家庭さん2名による体験談お話会がありました。
交流会
2025/12/01
提供会員勉強会「アウトドア防災ガイドに聞く 送迎時・預かり時の危険回避の仕方」
 日時:2025年11月20日(木)
日時:2025年11月20日(木)
場所:こども家庭センター「たまっこ」2階活動室
講師:あんどう りす 先生(アウトドア防災ガイド)
突然やってくる地震や水害。もしファミサポでお子さんを預かっている時に起きたら、お子さんやご自身、そしてご家族の安全を守るためにどう行動しますか?
アウトドア防災ガイドでテレビ・ラジオのパーソナリティ、内閣府や東京消防庁など公的機関での防災イベントでの講演を多数なさっている、あんどうりす先生に被災経験や専門知識に基づき、実験を交えながらお話していただきました。
災害の時に一番注意しなくてはいけないのは、真偽不明の情報です。SNSなどで拡散されている情報は、すべて正しいわけではありません。デマだったり、広く知れ渡った事柄でも安全面や衛生面に問題があるものが含まれています。安易に情報を拡散せず、情報の真偽を確かめることが大切です。そのベースとなる公的機関のアプリ情報を教えていただきました。
また、液体ミルクは直射日光をさけて35℃より低い温度で保存しなくてはいけないとか、子どもの誤飲防止の観点で防災グッズはボタン電池使用製品ではなく充電式の物がよい、圧縮タオルは子どもが誤って口に入れると危険‥‥など子どもの安全面から見たお話をたくさん聞くことができました。災害トイレの使い方や、洪水になった時に水の中を歩く場合どのくらいの圧力が脚にかかるのか、またVR眼鏡をつけて水害の中でマンホールなどを避けて歩けるかなど様々な体験もできました。
提供会員さんにとって、子どもが居るときの災害のイメージがふくらんだ時間になったことと思います。
勉強会
2025/10/27
全体交流会 0歳からのはじめてのオーケストラ
10月4日(土) 14:30〜16:00
ベルブホール(永山公民館5階)
出演:サロンオーケストラジャパン
「一緒に聴いて、踊って、体験しよう!」をコンセプトに、親子で楽しめるコンサートを全国で開催しているサロンオーケストラジャパンの皆様をお招きし、今年も全体交流会が行われました。子どもたちは、開場前から受付に用意されたドレスや帽子でおめかしして準備万端。ウェルカム演奏とともに、会場に足を踏み入れると、たくさんの楽器に自由に触れられるスペースが広がり、大人も子どもも楽しい時間を過ごしました。
オーケストラの演奏が始まってからも、楽器を持った演奏者さん達が客席に歩み寄って、間近で演奏を聴かせてくれるという珍しい演出に、子どもたちは大喜び!!演奏者さんと自由に写真を撮ることもでき、耳元で楽器の音色を楽しめました。
後半は、ワルツの音楽に合わせてみんなで輪になって踊ったり、楽しい音楽に合わせて子どもたちが指揮者になったり…最初から最後まで参加型のクラシックコンサートに、親子ともに笑顔があふれた一日でした。
交流会
2025/10/08
第64回提供会員養成講習会が終わりました。
今回の講習会は、前回までの講習で未受講科目が残った方、救命救急認定証の期限が切れる方(3年更新)、そして新規でお申込みいただいた方が参加してくださいました。講習会の日程は、3日間、5講座あります。「すべての日程に参加できないのだが」と参加を躊躇される方もいらっしゃると思います。講習会は、2月、5月、9月の年3回ありますので、今回受講できなかった講座は、次回以降の講習会で受けていただければ大丈夫です。また、お仕事や市民活動などでお忙しい方でも空いている時間や曜日だけでも、多摩市の子育て支援に協力していただけると嬉しいです。まずは無理のない範囲から子育てのお手伝いをしていただけませんか?次回は2月の土曜日を予定しています。
9月17日(水)『普通救命救急講習』 多摩消防署
9月19日(金)
『子どもたちの今と子育て支援の必要性』
・松田 妙子先生(NPO法人 せたがや子育てネット)
『子どもの理解と遊び方』
・池川 恵美子 先生(関戸みどりの保育園)
9月25日(木)
『子どもの健康について』
・飛田 正俊 先生(唐木田こどもクリニック)
『提供会員の活動について』
・多摩市ファミリー・サポート・センター
講習会
2025/07/25
提供会員勉強会「気になる子への関わり〜一人ひとりへの理解と配慮〜」
日時:2025年7月15日(火)
場所:こども家庭センター「たまっこ」2階活動室
講師:社会福祉法人 正夢の会
多摩市ひまわり教室 施設長 佐藤享美先生
今回の勉強会では、多摩市内にある発達支援施設、ひまわり教室の施設長・佐藤享美先生をお招きし、「気になる子への関わり〜一人ひとりへの理解と配慮〜」をテーマにお話しを伺いました。
ひまわり教室には、満2歳児〜5歳の発達に遅れや偏りがあるお子さんが通っており、ファミサポの活動の中で送迎などを通じて関わったことがあるという提供会員さんも多く、参加者にとっても身近な施設です。佐藤先生からはファミサポを通じて子ども達が地域の方々と繋がりをもてることの大切さについてのお話もあり、印象深いものとなりました。
今回「発達障害とは何か」という基本的な知識から、特性のある子どもたちへの具体的な支援の実例までとても丁寧に説明していただきました。なかでも、「特性」とは誰にでもあるもので、生まれ持った「脳のタイプの違い」であり、決して障害そのものではなく、本人らしさの一側面として尊重されるべきであるという考え方が心に残りました。
また、「氷山モデル」という視点での行動理解も紹介され、一見すると困った行動にも必ず背景や理由があること、そしてその子の気持ちに寄り添うことの大切さが伝えられました。
提供会員さんの皆さんにとっても、日々の活動の中で子どもたちと関わる上でのヒントが多く詰まった、有意義な時間となったのではないでしょうか。
佐藤享美先生、ありがとうございました。
勉強会
2025/05/24
第63回提供会員養成講習会が終わりました。
「子どもの健康について」では、西田 朗先生から、お子さんの様子に十分に注意してお預かりすることの大切さをお話しいただきました。発熱、下痢、嘔吐などよくある症状への対応の仕方、お子さんの年齢・発達、保育する室内環境によって起こりやすい事故をご指摘いただき、その予防策について教えていただきました。
「子どもたちの今と子育て支援の必要性」では、食を通して人がつながる子育てひろばを運営されている粟澤 稚富美先生から、親御さんやお子さんとの信頼関係を築くためのかかわり方のポイントをお話しいただきました。子育ての不安や悩みを抱えるご家庭が多いからこそ、様々な地域の大人たちとの出会いが大切であり、ファミサポの提供会員さんの存在は、親子にとって大きな支えとなると応援していただきました。
「子どもの理解と遊び方」では、かしのき保育園の近藤 直恵先生から、子どもの年齢ごとの育ちの特徴と大人のかかわり方・援助のポイントを、保育園の生活と合わせてお話いただきました。子どもの気づきや自発的な行動を環境を整えることで促すことができるよう、発達に応じた遊びの場や収納の工夫、手作りおもちゃの実物をご紹介いただきました。また、わらべうたを参加者も一緒に歌って、その心地よさを体験したり、お手玉を使って手遊びしたりと終始和やかな時間となりました。
5月14日(水)
『子どもの健康について』
・西田 朗 先生(にしだこどもクリニック)
『子どもたちの今と子育て支援の必要性』
・粟澤 稚富美 先生((公財)社会教育協会ひの社会教育センター)
5月20日(火)
『普通救命救急講習』 多摩消防署
5月22日(木)
『子どもの理解と遊び方』
・近藤 直恵 先生(かしのき保育園)
『提供会員の活動について』
・多摩市ファミリー・サポート・センター
講習会
2025/02/27
第62回提供会員養成講習会が終わりました。
「子どもたちの今と子育て支援の必要性」では、十文字学園女子大学の矢野景子先生に、育児だけでなく仕事・介護など抱える、孤立しがちな子育て世代を地域ぐるみで支えることが重要で、ファミサポの存在は子どもにより近く支援する立ち位置であるということをお話していただきましました。
「子どもの健康について」の清水伸泰先生には、子どもに起こりやすい病気やその症状、予防するための予防接種のとらえ方などお話ししていただきました。ファミサポの活動でお子さんを預かる判断基準にあたり「病後」とはどのような状態なのかなど様々な質問にも答えていただき、子どもを預かる上での参考になりました。
「子どもの理解と遊び方」では、バオバブちいさな家保育園の菊池久美子先生に子どもの発達段階と安全のための注意点について話していただきました。「子どもとかかわるうえで大切にしたい事」のアドバイスがあり、何気ない会話で子どもが安心感を高めるためには「おしゃべり上手」で、また「ほめ上手」のためには「かわいい」「すごい」「上手」などの言葉を使わずに、「〇〇ができたね」と事実を伝えてほめることで自己肯定感を高めることができるというお話は、とても参考になりすぐにでも試してみたいなと思いました。
2月8日(土)
『普通救命救急講習』 多摩消防署
2月15日(土)
『子どもたちの今と子育て支援の必要性』
・ 矢野 景子 先生 (十文字学園女子大学)
『子どもの健康について』
・ 清水 伸泰 先生 (こどもクリニックしみず)
2月22日(土)
『子どもの理解と遊び方』
・ 菊池 久美子 先生 (バオバブ小さな家保育園)
『提供会員の活動について』
・ 多摩市ファミリー・サポート・センター
講習会
2025/02/14
提供会員勉強会「実は私、発達障害でした」
 日時 : 2025年1月24日(金)
日時 : 2025年1月24日(金)
場所 : 子ども家庭支援センター 2階 活動室
講師 : NPO法人 えじそんくらぶ代表
高山 恵子 先生
「発達障害は理解と支援があれば個性になる、そして才能にもなる」という理念をお持ちの高山恵子先生をお招きし、お話を伺いました。実は高山先生は、30代になって初めて、ご自身がADHDであると診断されています。周りに理解者が多い環境の中で育つことができれば、社会人になるまで気づかないこともある「発達障害」。先生は周りにいい人がいてくれて良かったとお話されていました。先生が実際に経験された困りごとやどんなサポートが求められるのか、また薬剤師でもある先生ならではの「脳内物質」や「薬」の話も聞かせていただき、とても勉強になりました。
日本では発達にアンバランスのある子が厳しく育てられてしまうことが多いものです。見本と同じようにやることを求められ、努力して頑張ることが必要とされてしまいます。学校でも家庭でもない第三の居場所(それがファミサポの提供会員さんであることも多いのです!)があり、自分を理解してくれる人がいることで、やる気スイッチが入ったり、不安が消えていったりすることもあるのだそうです。
障害や特性を才能に変える環境があれば、子どもたちはありのままの不完全な自分も好きになることができ、自分らしく自己表現ができるので、発達障害という概念は不要になるのです。
高山先生、貴重なお話を聞かせていただき、どうもありがとうございました。
勉強会
2024/12/09
全体交流会 人形劇団ひぽぽたあむ
11月30日(土) 15:20〜16:00
関戸公民館(ヴィータ)8階大会議室
出演:人形劇団ひぽぽたあむ 『かえるくん・かえるくん』
「かえるくんのとくべつな日」「かえるくんのあたらしいともだち」
小さなひとたち(子どもたち)が、「かえるくん」の物語に入り込み、「かえるくん」に起こった出来事を、まるで隣で、一緒に体験しているような世界観に引き込んでくれた「ひぽぽたあむ」さんの人形劇でした。「かえるくん」やその仲間が活躍する舞台の前には、小さなひとたち専用のかわいらしいベンチが用意され、目を輝かせて見ている姿がとても印象的でした。劇が終わった後には、「かえるくん」とその仲間の人形たちが参加者をお見送り。小さなひとたちの心のなかに「かえるくん」とのひとときが刻まれたことでしょう。
交流会
2024/11/08
提供会員勉強会 赤ちゃん・子どもの救命応急手当講座「日常の事故防止と窒息&よくあるケガの手当」
 日時:2024年10月3日(木)
日時:2024年10月3日(木)
場所:子ども家庭支援センター 2階 活動室
講師:NPO法人シーボウル海の教室 中村智子先生
“赤ちゃん・子どもに特化した救命/応急手当”の講習会を全国で実施しているNPO法人シーボウル海の教室の中村智子先生をお招きし、貴重なお話をおうかがいしました。
赤ちゃんや子どもが日常生活の中で起こしやすい事故について、多くの親が心配する一方で、具体的な予防策や応急処置の知識を持っている人は意外と少ないのではないでしょうか。今回は家庭内で起こりやすい事故例を元に、「知っているようで知らない」、でも「誰もが知っておきたい」様々なケガの応急処置と窒息時の手当てなどを学びました。
子どもの成長段階に応じた窒息時の手当てでは、乳児・幼児の人形を使ったデモンストレーションがあり、参加者はエアーで実習を行いました。また、勉強会の最後には応急手当についてのカードゲームがあり、勉強会で学んだ内容を確実に復習する事ができました。
ファミリーサポートの活動ではもちろんの事、日々の生活の中で何か起きた時にすぐに実践できる内容は大変参考になり、参加者の方からも具体的な手当の方法でとてもよかったという嬉しいお声もいただきました。中村先生、ありがとうございました。